KurasuヘッドロースターのTakuyaです。3月末から4月上旬にかけて、オリジン(産地)訪問としてコロンビアに滞在しました。現地での品評会参加の様子をお伝えした前編に続いて、今回は農園視察レポートをお届けします。
前編でレポートしたCOLOMBIA WASHED COFFEE FESTIVAL(以下「CWCF」)が終わった後に、品評会に出品したなかの幾つかの農家の元を訪問しました。
最初に訪れたのは、FFTの代表であり生産者でもあるAlejandro Renjifoの農園。ウィラのサン アグスティンに位置し、今回の品評会の会場から車で1時間ほどの場所にあります。

標高1,700-1,900mの高地にある農園では、ゲイシャ、ティピカ、カスティージョなどの品種を栽培しています。彼のゲイシャとティピカは品評会でもハイスコアを獲得しており、ジャスミンのようなフローラルな香りとピーチやオレンジのような複雑な果実味が印象的でした。また、最もスコアが高かったのは彼の農園の中では標高が最も低い場所に位置するゲイシャで、標高が全てではなくコーヒーを取り巻くあらゆる環境がクオリティに繋がっていることを実感させられます。
彼の農園の名前である”Reina de Saba”は、旧約聖書に登場するシバ女王の逸話に由来しています。ソロモン王がどうしてもその手中に入れたかったシバ女王のように、どれだけロースターが望んでも簡単には手に入らないほどの素晴らしいコーヒーを生産したい、という想いが込められています。
そんな彼のゲイシャを今回皆さんに紹介することができ、嬉しく思います。

(農園主Alejandroと息子のSasha)
サン アグスティンを去った後は、同じウィラのタルキエリアの農家の元を訪れました。コロンビア全体にも言えることですが、特にタルキはアップダウンが激しい山岳地帯で、数百m離れると気候が変わるマイクロクライメイトがある場所です。そのため同じタルキの中でも、それぞれ個性的なコーヒーが生産されています。

CWCFで1位に輝いたCarolina Andrea Claros。品種としてはコロンビア、カトゥーラを栽培しており、コロンビアは初期(1970年代)から続く種を大切に守って育て続けています。品評会で1位になったことについて「神様のおかげです」という謙虚な姿勢を見せながらも、クオリティに関して非常に厳格に生産に取り組んでいる様子が印象に残っています。

農園主のCarolinaは元々コーヒー農家の家系で、生まれた時からコーヒー生産に関わっており、クオリティが高いコーヒーを作りたいという想いを抱いています。
「クオリティが収入にそのまま影響する仕事なので、自分が成功することで、自分の子供や周りの人間のモチベーションをあげたい。周りの模範になるように仕事をしている」と語るCarolina。コロンビアに限らず、コーヒー生産が行われる多くの国では、離農や跡継ぎが不足していることが課題となっています。
実際に他の農家の方と話した際も、「息子がボゴタで役所の仕事に就いてしまって働き手がいない」という話を聞きました。Carolinaは、こうした課題に対して、コーヒー生産という仕事の魅力を伝えようとしているのです。
今回の品評会で得た収入は、チェリーを移動させるためのバイクを購入するなどの投資に充てたいとのこと。1位になったカトゥーラ-コロンビアは、この彼女の姿勢がそのまま表れたような、コロンビアのテロワールが見事に表現された素晴らしいカップでした。
タルキの農園では、アップダウンがある土地特性上、チェリーの運搬に負荷がかかります。Carolinaの農園では現状馬を使って運んでいますが、他の農園では様々な手法が見られました。

上の写真は、木でパイプを作り、中に水を流して標高が高い場所から低い場所へチェリーを移動させる設備です。
また、下の写真はチェリーを入れた籠を置いて運搬ができるレールのような設備。上から下だけではなく、下から上へも運搬が可能です。

特別に乗せてもらいました
コロンビアでは、コーヒー生産者のうち94%が5ha以下の小規模農家で、10ha以上の大きい農園を持つのはわずか1%。こうした設備は全ての農家に普及しているわけではなく、農家によって設備の質と量にバラつきがあるのが現状です。
その後は車で7時間ほどかけて、トリマのガイタニアに移動しました。このエリアは、雨季と乾季にはっきりした境界がなく、年中雨が降り続けるような気候が特徴です。そのため年中収穫が可能ですが、チェリーの成熟のバラつきによってピッキングが難しかったり、チェリーの落下が頻繁に起こったりするため、収穫に一層気を遣う必要があります。また、近年の気候変動でラニーニャ現象の頻度も高まっており、降雨のタイミングの予測が難しくなってきています。

農園訪問中にもスコールが。
CWCF5位のCarlos Sotoは、祖父からコーヒー農園を受け継ぎ、コロンビア、カスティージョ、セニカフェを栽培しています。カサエルタというトリマの伝統的な乾燥方法を用いており、建物の屋根が可動式になっているため、天候に応じて乾燥を進めることができます。パルピング後30時間水なしで発酵させたあと洗浄し、最初にそのカサエルタで4-5日一気に乾燥させ、その後パティオで2-3週間天日乾燥させることで、適切に水分値をコントロールしクリーンな味わいを作り出しているようです。こうしたプロセシングのやり方は最近近所の生産者に教えてもらったらしく、Carlosも品質が良くなっていることを実感しているそう。

まだCarlos自身はカップが取れないですが、今後生産者団体のオフィスでトレーニングしたいと話していました。コーヒーをカッピングすることに興味がある生産者は決して多いわけではありません。こうした姿勢からも、彼の農園のコーヒーはこれからもどんどん良くなっていくだろうと感じます。
その後、同じガイタニアのLisandro Quilcueの元を訪問しました。Lisandroは、3年前に初めてKurasuで購入して以降、継続的に取引を続けている生産者です。今回初めて農園訪問が叶い、本当に嬉しく思います。

彼の農園は、ナサ民族というコロンビアの少数民族によって運営されています。ナサ民族のコミュニティでは独自のカルチャーや言語が発展しており、今から28年前にコロンビア国と彼らの間で平和協定が結ばれました。コロンビアという国の中でも、彼らの存在は非常に貴重なものになっています。コーヒー生産は彼らの生活の中心にあり、Lisandroはナサ民族のリーダー的存在です。
「クオリティの良いコーヒーをつくる姿を周りに見せていく」ことが大事だとLisandroは言います。「コーヒーは私たちナサ民族にとって大事な産業。皆が自分の後に続いていってほしい。」私たち消費国は、彼らのコーヒーを適正価格で買うことが一番の支援になります。今後も継続的にみなさんに紹介していきますので、ぜひ一度彼のコーヒーを飲んでみてください。

最後に訪れたのは、Astrid Medinaの農園 Buena Vista。彼女は2015年にCOEで1位を獲得した実績があり、その品質の高さは言うまでもありませんが、彼女はその売上で得たお金の全てや毎年の収入の大半を、農園の設備投資やピッカーたちの労働環境の改善に当てています。自分が良い暮らしをするよりも、周りの人々やコーヒーに関わる人のためにお金と時間を注ぎ込んでいます。

私たちが彼女の農園を訪れた際も「誰かの靴を履いてみるまでは、他人の苦労を本当に知ることはできない」と語り、訪問した私たちロースターに感謝の言葉を述べてくれました。実際に相手の立場を少しでも体験してこそ、その大変さが分かる。文字にしてみると至極当たり前のことかもしれませんが、実際農園に訪れることで、その現場で起こっていることの全てが私たちが普段飲んでいるコーヒーに繋がっていることを体感しました。ピッキングやソーティング、土壌、気候、食事や寝泊まりする場所でさえ、肌で感じる環境すべてが繋がっているのです。

彼女のコーヒーは3年続けて購入してきていますが、一貫して感じるのは繊細で花やか、けれども芯のある甘さがある印象。私が彼女という人間に対して感じた印象と近しい部分があります。周りの人間に対して思いやりと愛情があり、自分の軸を決してブラさない。そんな彼女のコーヒーを今後も紹介していけることが嬉しいです。

今回のコロンビアへのオリジントリップを通じて、一杯のコーヒーの裏にあるストーリーの複雑さと、買う側の選択がいかに未来のコーヒーの在り方に影響するかということを改めて実感しました。素晴らしい機会を提供していただいたSYU・HA・RI、Fair Field Trading、そして生産者の皆さんに感謝いたします。
今後リリースされるコロンビアのコーヒーを、ぜひお楽しみに。
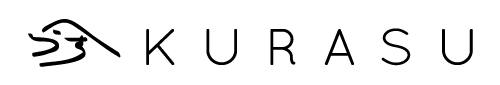
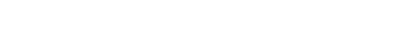
![【プレミアム】エクアドル ルグマパタ シドラ [浅煎り]](http://jp.kurasu.kyoto/cdn/shop/files/image_Beans_Premium-Ecuador-Lugumapata-Sidra.jpg?v=1765955538&width=104)
![シーズナルブレンド・冬萌 2025 [中煎り]](http://jp.kurasu.kyoto/cdn/shop/files/image_Beans_Blend-FuyuMoe_2025.jpg?v=1764809508&width=104)





