#STORY

EMBANKMENT COFFEE (大阪)2017年4月の #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#クラスパートナーロースターは、大阪のEMBANKMENT COFFEE(エンバンクメントコーヒー)。 EMBANKMENT COFFEEが店を構えるのは、大阪・北浜。大阪の商業の中心地だった船場の北の端に位置し、現在では史跡や当時をしのばせる建造物と、金融街らしく立ち並ぶ高層ビルとが混在している。暖かい日には土佐堀川沿いで川床を楽しむ人々が訪れるこの地は、若者の街と評される...
#STORY
KARIOMONS COFFEE ROASTER (長崎):2018年3月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#kurasupartnerroaster(Kurasu提携ロースター)は長崎のKARIOMONS COFFEE ROASTER。 時津町にある1号店は、倉庫を利用した店舗だ。トタン板の壁、ドラム缶や灯油ストーブといったノスタルジックなインテリアに、ステンレスが蛍光灯を反射する実験室のようなコーナーや、木材が貼り合わせられた大きなカウンター、メカニックな存在感のあるプロバット...
#STORY
AND COFFEE ROASTERS (熊本): 2018年2月 #クラスパートナーロースター
今月ご紹介する #kurasucoffee サブスクリプション提携ロースターは、熊本県のAND COFFEE ROASTERS。代表の山根さんに、お話を伺った。 山根さんがコーヒーと出会ったのは、ニューヨーク。19歳のころ、短期留学中だった山根さんはルームメイトを通してカフェやコーヒーの文化に魅了されたという。帰国後、カフェやロースターで働きたいと思い探すものの、自分がニューヨークで恋...
#STORY
TRUNK COFFEE (名古屋): 2018年1月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#kurasucoffee提携ロースターは、名古屋のTRUNK COFFEE 。Kurasuが始まった頃からお付き合いいただき、私達が長く尊敬するロースターだ。オーナーの鈴木さんに、改めてお話を伺った。 サラリーマン時代、そして旅への予感 旅行代理店であるHISで社会人生活をスタートさせた鈴木さん。現在共に経営を担い、ロースターとして活躍する田中さんは実は職場の後輩にあたる。...
#STORY
LiLo Coffee Roasters (大阪): 2017年12月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介するロースターは、大阪・心斎橋のLiLo Coffee Roasters。 心斎橋といえば、エリアによって様々に印象が変わる場所、そして、常に変化を続けている場所として、活気ある大阪の中でも特に注目を集めている。 LiLo Coffee Roastersが位置するのは、そんな心斎橋エリアの中でも若者の街として知られているアメリカ村。70年代にアメリカ西海岸からの...
#STORY

TAOCA COFFEE (兵庫) : 2017年11月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#kurasucoffee サブスクリプション提携ロースターは、兵庫・TAOCA COFFEE。多くの人の愛される苦楽園店に続き、今年岡本に新店舗、タオカコーヒー OKAMOTO KOBE を構え、その着実な成長ぶりがうかがえるスペシャルティコーヒー専門店だ。店主の田岡さんに、お話を伺った。 岡本駅を出てすぐに現れるタオカコーヒー OKAMOTO KOBE。周辺の道には石畳...
#STORY

Passage Coffee (東京) : 2017年10月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#クラスパートナーロースターは、東京・田町のPassage Coffee。 三田通り沿いにある店舗の前に立てば、視線のまっすぐ先に東京タワーが見える。大学があり、オフィス街であり、また観光地でもあるという土地柄、日常と非日常がいそがしく行き交うこの場所では、人通りが途切れることはない。 店内は明るく、木材で統一された内装と、交差するいくつもの直線で構成されていながら暖かみの...
#STORY

Townsquare Coffee Roasters (福岡: 2017年9月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#kurasucoffee サブスクリプション提携ロースターは、福岡のTownsquare Coffee Roasters。コーヒーカルチャーの成長著しい福岡でもひときわ目を引くスペシャルティコーヒー専門店だ。その中核を担う井手さんにお話を伺った。 井手さんはどのようにコーヒーに関わる道に入られたのでしょうか? 昔はパティシエとして働いていました。元々コーヒーは飲めなか...
#STORY

27 COFFEE ROASTERS (神奈川) : 2017年8月 #クラスパートナーロースター
次にご紹介する#kurasucoffee サブスクリプション提携ロースターは、神奈川県藤沢市、辻堂に位置する27 COFFEE ROASTERS。神奈川県を代表するスペシャルティーコーヒーロースターになるまでの20年間の歩みについて、代表の葛西さんにお話を伺いました。 コーヒーの世界に入ったきかっけ、今までの道のりを教えてください。 実は店を始めてもう20年になります。1997年に...
#STORY

Saredo Coffee (福岡) : 2017年7月 #クラスパートナーロースター
次に#kurasucoffee サブスクリプション提携ロースターとしてご紹介するのは、福岡のSaredo Coffee。明るく暖かみのある店内で、店主の権藤さんに、お話を伺った。 1.コーヒー業界にはどのようにして入られたのですか? コーヒーと関わり始めたのは、スターバックスでバイトを始めたのがきっかけです。雰囲気の良さにひかれて、10年ほどいました。それまではコーヒーといえば甘い...
#STORY

Finetime Coffee Roasters: 2017年6月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介するのは、東京・経堂にあるFinetime Coffee Roasters。オーナー・ロースターの近藤さんにお話を伺った。 Finetime Coffee Roastersがオープンするまでの経緯を教えてください。 元々はセゾングループで流通や財務に携わっていました。 そこで社内の留学制度を利用して、MBAを取得するためにミシガン大学へ進学した後、10年ほどモル...
#STORY

COFFEE COUNTY: 2017年5月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介する#クラスパートナーロースターは、福岡県久留米市にあるCOFFEE COUNTY。ロースター、オーナーの森崇顕さんにお話を伺った。 -COFFEE COUNTYができる以前の経緯をお聞かせいただけますか? コーヒーカウンティを始める以前はタウンスクエア コーヒーで勤めていました。大きな焙煎機で焙煎するような仕事や、その後コーヒー豆と器具を取り扱うお店...
#STORY

4/4 SEASONS COFFEE:2017年4月 #クラスパートナーロースター
東京・新宿の4/4 SEASONS COFFEE (オールシーズンズコーヒー)が次回のKurasuのコーヒーサブスクリプション 。ロースターの齋藤さんに、焙煎との歩み、お店ができるまでのお話を伺った。 大学1年の頃、地元熊谷駅のスターバックスに初めて立ち寄り、その場でアルバイトに応募。テイクアウトカップのリッドの用途すら知らなかったところから、コーヒーの世界に飛び込んだ。当時ス...
#STORY

Basking Coffee (福岡): 2017年3月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介するロースターは、Basking Coffee。 全面ガラス張りの大きな扉をくぐり店舗に足を踏み入れまず感じたのが、天井の高さ、そして空間の圧倒的な明るさだ。インテリアは背の高い観葉植物や、木材、鉄を組み合わせたナチュラルな建具で構成され、光のあふれる店内では皆が親しげに言葉を交わしながら過ごしている。 前回に続き、福岡、そして世界を飛び回り活躍するロースターの榎原...
#STORY

MANLY COFFEE: 2017年2月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介するロースターは、福岡のMANLY COFFEE。精力的に店を切り盛りし、日本エアロプレスチャンピオンシップ実現の立役者でもある須永さんに、お話を伺った。 MANLY COFFEEができるまで スターバックスで勤務していた頃、ブラックエプロンチャンピオン、つまりスターバックスジャパンのトップバリスタとして、シアトル研修を経験するなど、子育てと両立しながら業界で活...
#STORY

Oyamazaki Coffee Roasters: 2017年1月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが次にご紹介するロースターは、京都の大山崎COFFEE ROASTERS。 シンプルな原点を大切に、物事の優先順位を、そしてその理由を忘れない。簡単なように思えて、実は最も難しいこの姿勢。忙しい日々に追われながら、「今の自分の生活はこれでいいのだろうか」という問いがふと頭をよぎった事がある人は少なくないだろう。そんな問いに真正面から向き合い、自分たちの道を切り開いたのが大山崎C...
#STORY

Hoshikawa Cafe: 2016年12月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが2017年最初にご紹介するロースターは、埼玉のホシカワカフェ。 日本一の猛暑日を記録し一躍話題になった熊谷市だが、普段はゆるやかなペースで時の流れる、落ち着いた場所だ。カフェの名前の由来ともなった星川沿いには彫刻が木漏れ日を受け、せせらぎの音の気持ち良い遊歩道がある。 そんな光あふれる散歩道にあるホシカワカフェで、店主の鈴木さんにお話を伺った。 店内は明るい色合いの内装と大きな...
#STORY

Life Size Cribe: 2016年11月 #クラスパートナーロースター
芯のある声で「何でも聞いてください!」と、快く取材に応じてくださったのは、国分寺にあるLife Size Cribeの吉田さん。 Kurasuのコーヒーサブスクリプションで提携するカフェ・焙煎所だ。 新卒時、縁があり決まった飲食業界の企業で、コーヒーに関わる仕事をスタート。持ち前の向上心と行動力を活かし最短で店長に就任した。日々喫茶店という場への思い入れは高まり、勤務開始まもな...
#STORY

MEL COFFEE ROASTERS: 2016年10月 #クラスパートナーロースター
Kurasuが11月にご紹介するのは、大阪のMel Coffee Roasters。 大阪を代表する活気ある街の一つ、心斎橋。大通りを曲がり、オフィスビルや住居ビルが並ぶ落ち着いた横道を進むと、十字路の角にMel Coffee Roastersが現れる。 街並みに溶け込むシンプルな外観だが、近づいてみると手塗りの跡も感じられるような素朴な外壁に、控えめに踊るようなロゴが目にも...
#STORY

WEEKENDERS COFFEE: 2016年9月 #クラスパートナーロースター
Kurasuから次にお届けするコーヒーは、京都のWEEKENDERS COFFEEから。 京都、富小路通りに佇むのは、白塗りの壁に植木の緑もまばゆい小さな町屋。年月の流れを感じさせる艶のある木柱がモダンな建具と調和し、隅の方にはふくふくと丸く身を寄せ合う苔庭や小さな腰掛が懐かしさを誘う。日本家屋独特の開放的な入り口の向こうにあるのは、7月にオープンしたばかりのWEEKENDERS COFF...
#STORY

LIGHT UP COFFEE : 2016年6月 #クラスパートナーロースター
学生の頃から、人生を賭けて追いかけたい夢に出会える人は少ないだろう。しかしLIGHT UP COFFEEのオーナー、相原民人さんと川野優馬さんはそんな数少ないうちの二人。彼らは在学中に、「コーヒー」という夢に出会った。 当時相原さんはデザイン学専攻、川野さんは経済学を専攻していたが、フランチャイズコーヒーチェーンでラテアートに出会い、その魅力にとりつかれる。心を込めてサーブしたときのお...
#STORY

Thank you so much to our coffee subscription members for your continued support. We've received a message from Kawai san - the director of Golpie Coffee, February's featured roaster - on his expe...
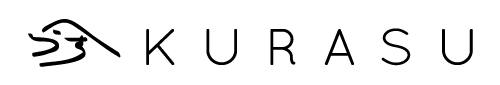
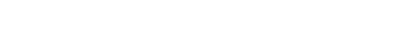

![[送料無料] 100g x 3種類のシングルオリジンコーヒーセット](http://jp.kurasu.kyoto/cdn/shop/files/image_Beans_Nomikurabe_single.jpg?v=1742880468&width=104)
![ハウスブレンド ダーク [深煎り]](http://jp.kurasu.kyoto/cdn/shop/files/image_Beans_Blend-Dark.jpg?v=1742880472&width=104)


